<金曜は本の紹介>
この「世界で通用するリーダーシップ」という本は、東大卒業後に川崎製鉄へ入社し、その後米国大学院で修士号を取得し、ボストンコンサルティンググループ入社、日本ゼネラル・エレトリック(GE)入社、GE航空機エンジン北アジア地域社長、GE横河メディアルシステム代表取締役社長、現在ノバルティス ファーマ社長を務める三谷宏幸さんが、その経歴やその経歴で学んだ現場主義、リーダーシップ、教育、変化に対応、企業の強みなどについて書いたものです。
特に学生時代の苦悩やGE社長だったジャック・ウェルチの逸話等については、とても興味深かったですね。
ジャック・ウェルチには48hルールがあり、何か失敗して48h以内に連絡がなければクビにはならないというのは面白いと思いました・・・^_^;)
とてもオススメな本です!
以下はこの本のポイントなどです。
・いつも現場から、仕事は始まっていた。経営者になっても、それが変わることはなかった。2007年、54歳でノバルティス ファーマの社長に就任したときも、まず私が取り組んだのは、現場に行くことだった。3ヶ月で事業所16カ所。1400人の社員に会った。事業所ではできる限り全員に集まってもらって、直接いろいろな話をしたり、聞いたりした。どうして現場からだったのかというと、それが経営の第一歩だと私は考えているからである。経営者が取るべきアクションの最たるものは何かといえば、従業員を元気づけることであり、コミュニケーションである。現場にいくことが、どうして経営なのか、という人もいる。その重要性に、どういうわけだか気づかない人がいる。しかし、これこそが経営だと私は思うのだ。現場にトップが行くことで、人と組織がかみ合うのである。私は経営とは、社内の人の力をどう使うか、が最も重要な要素だと考えている。なぜなら、どんなに優れた戦略も、プロジェクトも、それらを担うのは人だからである。経営とは、最終的には戦略やプランではない。人を動かすことが経営なのである。
・最近、若い人に仕事やキャリアのアドバイスを求められることがよくある。何より思うのは、悩みには正しい答えは存在しない、ということだ。もし会社を辞めて右なら右の道に進んだとしても、成功が保証されているわけではない。では、左に進んで会社に残ったからといって、やはり保証はない。どっちに進めばいいのか、結局は正しい答えはないのだ。もちろん個人の適性は存在するが、個人の未来は予知できない。そういうときの私のアドバイスはこうである。「その悩みを自分で真正面から受け止めて、真剣に悩み抜くことだ。そして、どちらを選んでも後悔しないことだ」と。要は答えがわからない中で、どれだけ自分らしく生きていけるか、結局はそれに尽きる。
・あのポジティブさは、日本人は絶対に学んだほうがいい。そもそも日本人は物事をネガティブに考えがちだ。いくら優秀でも、ネガティブな発想が多いと、議論が建設的ではなくなってくる。それどころか、人の話も聞こうとしなくなる。これでは絶対に成長も成功もありえない。一方、米国人はポジティブな発想で物事に臨み、必要とあれば自分までも変える。自分をどんどん変えて、最後は目指す価値に自分を合わせていくことができるようになる。こうした進化は成長に不可欠なものだ。
・後になってもう取り返しがつかないときに自分の立場を嘆くことになるよりは、今のうちに挑戦するという選択肢を持つべきだ。もちろん、何でもいいから新しいことや違うことをやっていればいいという話ではない。転職を繰り返せという話でもない。自分を成長させ、自分の器を広げるために、あえて努力をしなければいけないということだ。まずはこれで十分だろうかと常にシビアな目で現状を観察することから始めてほしい。感性が働く若いうちであれば、挑戦は自分の血肉になっていくだろう。
・「感性」を磨くことは簡単ではない。しかし不可能でもない。じゃあどうすればいいのだろうか。たとえば社外の人たちと会って、違う環境の中から、共通する考え方を見つけ出す。あるいは、売るほうからの視点だけで物を見るのではなく、買うほうの視点から同じ物を見てみる。こうした視点の変更などは「感性」を磨くために重要な行動になってくる。
・私は「感性×経験」がビジネスの成功を決めると考えている。経験だけでは、世の中の変化に対応できない。一方「感性」だけでは、習得したノウハウの蓄積を活かせない。それを継続的に繰り返して学び続けていく。ところが、時間をかけて経験だけを積ませて、それで困難な状況を乗り切ろうとする企業が後を絶たない。だから、同じ思考サイクルから進化して次の段階に進むことができない。日本が弱くなってしまった要因は、ここにあると思う。かつてはずっと右肩上がりの成長がずっと維持できたから、同じことをより効率的にやっていさえいればよかった。ただ現在のように変化が加速化しているときには、もはやそうした前提条件が変わってきている。視点をあえて変えていかなければ将来の変化が見通せない。もういい加減日本人も居心地のいい場所から脱出しなければいけないと思う。
・求められているのは、こうした変化なのだ。自分たちにできることを必死で見つめ直し、自分たちの国に合った新しいビジネスモデルを作る。戦後の日本には、何もない混乱の中で、そういうことを考えた人たちが大勢いたのだと思う。その人たちが勝ちパターンを構築し、次の人たちがそれを引き継いで、大きな成功へと導いていった。ところが、そうした創始者たちの後には、フォロワーが必要となる。フォロワーはある面では不可欠な存在だが、残念なことに日本は大勢のフォロワーだけを継続的に生み出してしまうしくみまで作ってしまった。要するに、言われたことをいかに完璧にできるかということが国にとって最も大きな価値となってしまった。しかも、これを偏差値教育や減点主義が増長させ、次の時代に向けての創造ができなくなってしまった。成功の報酬というべきしっぺ返しがやってきたといえる。
・今、求められているのは、破壊して作り上げる作業である。それができるかどうかを、我々は問われているのだ。しかし、状況はなかなか好転してこない。ここで必要なのは、感性と気概なのかもしれない。かつて戦後の日本には、そうした”志”があった。そして時代の転換期において、人々が理解できないほどの大きな改革を提言し実行しようとした政治家はいつも大きな抵抗にあった。私はこれが本当の改革だと思う。
・自分ひとりで何でも直接やっていくのは無理だ。したがって、いかにして部下に前向きに働いてもらうか、部下からどうやって情報を吸い上げるかということが重要になってくるのは言うまでもない。組織というテコをうまく活用する方法を学べたのは自分にとって大きな進歩だった。加えて、相手をほめることの重要性にも気づいた。お客様を一緒に訪問して、よく部下に言った。「君が言った通りだったな」「でも、こういうところはちょっと違った。君はどう思う?」・・・。これは後々、自分の仕事の定番のやり方になっていく。たとえ早いうちに自分に答えが見えていたとしても、情報収集や意思決定のプロセスは部下と一緒に行う。そうすることで、部下と認識を一体化することができ、実際にアクションを実行してもらえる確率が上がり、ひいては成功する確率も上がる。いくら質の良い答えを出したとしても、相手が必ずしもそれを聞いてくれるわけではないということは、コンサルタント時代にも何度も経験していたことだった。それは部下に対してのみならず、また会社全体の意思決定についてでも同じことがいえる。これはと思った部下と答えを一緒に作っていくプロセスこそが相手を納得させることにつながる。
・一般的に、事業が厳しい状態になっている、たとえば営業成績で負けている、こういうとき現場で話を聞くと、敗因として、いつも次の3つの理由が出てくる。「価格でやられました」「お客さまとのリレーションシップ不足でした」「品質が圧倒されました」と。こんなとき、社外のコンサルタントに依頼して、いくら精微華麗に分析しても、同じ結果しか出てこない。当然である。元のデータを提供する現場の営業当事者たちが3つの理由しか挙げてこないからだ。従って本当の敗因を追求するためには、彼らの見方を真に受けるのではなく、「理由は本当にこの3つだけなのか」というところから原因分析を始めなければいけない。
・私は営業担当者と一緒に、窓口の購買部だけではなく、企画部、整備本部、運航本部など”点”を超えた”面”での対応を取ることになった。どの部門が、どの部門に影響力を持っているのか。どの部門の誰の話なら、社内に影響力を及ぼすことができるのか。こうした考え方や物事の見方は、通常の営業担当者はあまり意識していない。本来は顧客の組織の中で動きを起こせるくらいまで、付き合いを広げるべきだ。そのためには上司はできるだけ多くの現場に顔を出して部下を指導する必要がある。そしてしかるべき管理職同士の会話の中から相手との関係を広げていく。その意味ではときどき上司が担当者に同行するくらいでは、深い関係は構築できない。そして、トップ自らも当然現場に出て行く。トップが出て行くからこそ、聞き出せる話がある。会ってもらえる部門や役職者がいる。トップはそうした面を広げるために、自らを部下に利用させるべきだ。トップは「売上を作れ」と言っているだけでは、簡単に売上は作れない。厳しい状況からは脱却できない。トップは現場で起きていることをしっかり理解して、具体的な指示を出さなければいけない。それが、本当の意味で「組織を動かす」ということだ。
・本来は、企業は将来有望な人材を早いうちにいくつかの職種を経験させないといけない。たとえば、私はGEに入って6年で経営トップを経験することになったが、私の経営に対する経験は極めて少なかった。しかし、そんな私がトップになれたのは、将来性を買ってもらえて早いうちにいろいろな経験をさせてもらえたからだと思う。「誰かが自分のことを信じてくれた」。人はいつもそういう誰かに支えられているのである。ではなぜ、外資はそういうことをするのか。理由は簡単だ。それは将来のリーダーたるポテンシャルを持っている人材をトップに据えないと、そして早期にトレーニングを受けさせないと、会社が将来的に大きく成長することは難しいとわかっているからである。
・優れた人間というのは、問題点がどこにあるかは、常に把握しているものだ。上司に問いかけられて答えられないのは、脇が甘いと思われても仕方がない。世の中では組織を引っ張る立場にありながら、客観的や論理的ではなく感覚的に物事を判断するといったリーダーたちをよく見かける。こういう判断は多くの場合一貫性に欠ける。また、こういうリーダーたちは往々にして厳しい判断を回避しがちになる。なにも人に優しくするなと言いたいのではない。時として厳しい現実を見つめたがらないこうした発想が、自分自身に甘えを生んでいるということを言いたいのだ。リーダーたる人たちはいつも気を抜かずに、物事に厳しく集中して取り組むべきだということをわかってもらいたい。人の本当の能力というんは、不思議にいろいろなところに出てくるものである。問いかけに対する返答であったり、ちょっとした行動だったり、わずかに見せる態度だったり。だからこそ、人は5分で判断ができるし、されるのだということを覚悟しなくてはいけない。
・今そうした組織に求められているのは、”伝統の継承”ではなく”変化を読みとる”力である。そのために必要になってくる手段が、ダイバーシティなのだ。こうした変化を読みとる力を高めるためには、女性や外国人を登用するのは、当たり前のことで。したがってダイバーシティは女性や外国人の採用を拡大するためのスローガンではない。会社が存続していくために必要不可欠な手段なのである。そしてダイバーシティは、さらなるダイバーシティを生み出してくれる。たとえば、ノバルティス ファーマでは、女性の営業所長が二人誕生した。こういうニュースのおかげで、意欲を持った女性が会社に集まりやすくなってきている。こうした連鎖反応は起こりやすい。
・ウェルチのすごさは、部下を萎縮させることもあったが、圧倒的に元気にさせていたところである。これこそ、と思うリーダーや案件があれば、彼は徹底的にサポートした。方法論も教えるし、権限も与えるし、当然話も聞く。数字が悪ければ萎縮することになるわけだが、選ばれて何回かそのテストをパスした人たちは、よほどのことがない限り、いろいろと助けてもらえることのほうが多かった。個人を認め、その能力を引き出してくれる”温かさ”がそこにあった。
・彼が会議の際に時折我々に見せた厳しさも、結局のところ、自分たちが厳しく仕事に向かうための精神注入の一環だったのだろう。苦労してできなかった事柄が努力の結果できるようになると、ウェルチはちゃんとそれを認めた。信賞必罰ではあるけれど、単にドライなだけではない。部下との接し方や育成の仕方は、本当にすばらしいと思った。そうした行動の背景にあるのは、人を育てることによって、会社が良くなっていくという信念である。自らはCEOとして、人を育てることが一番大事なミッションだと彼がよく語っていたのを覚えている。実際のところ、彼は自分の時間の5割近くを人事に使っていたと思う。だからこそ人について厳しく判断できるだけの情報をちゃんと持っていた。当時35万人いたGEの社員のうち、3000人以上の幹部の名前をウェルチは知っていたと言われている。それでも、幹部はクビになるときはクビになる。日本でも、来日するたびに幹部の1人か2人がいなくなる場面に遭遇した。しかし、ただこうしたクビになった幹部には、あっという間にヘッドハンターから声がかかり、就職の引く手はあまただということもまた事実だった。GEで鍛えられ、ある程度のポジションを勤めていたというだけで、人材市場では大きな実績となった。だから、クビになることは、新しいチャンスの到来をも意味していたのだ。
・GEには当時”48時間ルール”というものがあって、幹部にクビが宣告されるときは、そのきっかけから、48時間以内に連絡が来るという不文律のルールがあった。私は静かに連絡を待った。2日以上たって一通のメールが来ていたことに気づいた。ウェルチ本人からではなく秘書からのメールだったので、すぐには気づかなかったのだ。背中に寒いものが走った。でもできるだけ動転しないようにゆっくりメールを読んだ。それは、3行ほどの短いメールだった。「ミタニ、お前はいつもお客さまのことを考えている。我々はお前のやっていることを認めている。頑張れ」と。「もし何かあったら我々に言ってほしい」と、対応が十分にとれていなかった米国本社の関係部署の幹部も心から事態を心配してくれていた。その幹部からも時を同じくして私に連絡が来ていた。(ウェルチと)「よくやったね」と。二通のメールを見て思わず涙が出てきた。
・私が何よりGEが好きだったところは、実はそうした文化だった。フェアな姿勢をみんなが評価してくれる。早い抜擢がある会社だけに、足の引っ張り合いがあってもおかしくなかったが、不思議にそういうことはなかった。そこが良かった。みんなが自分に自信を持ってクリーンファイトをしていた。
・製薬業界におけるノバルティスを見てみると、大きくは3つの強みがあると私は思う。まずは「規模」、次に「開発力」、最後に強みを再生産していくための「人と企業文化」というソフトの強さがそれを裏打ちしている。実はこの枠組みは、業界が違っても大して違いはないと思える。まず最初の「規模」が会社の安定性を作る。つまりどこかの国や製品で問題があっても、それを補完する代替が存在する。したがって売上を常に安定させることができる。たとえばGEでも複数の業界にその事業基盤を持っている。これをGEは、多様化された事業ポートフォリオと呼んで、安定的な成長を維持するための事業戦略の中心となっている。できるだけ違う産業に軸足を置き、どこかの事業での売上ロスは、他の事業でオフセットできるという体制である。ノバルティスも事業の多角化を進めており、加えて世界140カ国以上での事業の発展は、安定的な売上の基盤作りに寄与していた。次に製薬業界においては、「製品開発力」が差別化の要になるのは言うまでもない。10年も20年もかけて新薬を開発するのは容易なことではない。しかしそれがひとたび大型製品となって当たると、向こう十数年以上の定常的な売上を保証する。
・最後に「人と企業文化」について述べる。これはどの企業や産業にとっても、最も重要な強みを形成する要素といえる。先にも述べたが、どうやって意図的にリーダーを育て、成長しようとする文化を育むかは、企業の将来の成長に対する”起動力の違い”となって出てくる。これは一見、簡単に獲得できる強みのように見えて、実は最も困難で、時間のかかる差別化因子であると私は思っている。
<目次>
はじめに
第1章 いつも何かを探していた-流れに逆らう人生を選ぶ
灘中・灘高から東大を目指す
東大受験失敗とモラトリアム
東京で受けたカルチャーショック
行きたかった商社をあきらめる
川崎製鉄に入社し、現場に入る
「アメリカのビジネス・エリート」との出会い
経営をやってみたい-米国へ留学
第2章 日本と米国、考え方の違い-グローバルな視点が人生観を変える
自由だけれど自己責任が問われる
「予定調和」と「ビルディングブロック」
できることの幅が米国は広い
UCバークレーからスタンフォード大学へ
退社を決断-自分が燃えることをしたい
ポジティブな発想で答えを出そうと努力する
人生やキャリアは「足し算」ではなく「掛け算」
第3章 経営の理論を学ぶことから実践へ-「感性×経験」がビジネスの成功につながる
経験だけで経営者になれるのか
やはり実践でなければわからない
GEで学んだ本当の経営とリーダーシップ
経営に大きな力を及ぼすのが「感性」
「感性×経験」がビジネスの成否を決める
破壊がないと創造がない
社長は守りと攻めの要
悲壮感を持っている会社にはチャンスがある
事業の持続性
第4章 企業の成長をドライブする-落ちた業績をどう立て直すか
GEの変化のまっただ中に飛び込む
いかにして部下を巻き込むか
「プレイ・インジャード(Play injured)」
敗因の”三大理由”は正しいのか
顧客との接点は”点”ではなく”面”で考える
「三つのことだけ守ってほしい」と伝える
効率改善の落とし穴
「効率」と「効果」
第5章 外資系に勤めるということ-ロジックと情熱
社員のリーダー養成法
内資と外資のキャリア比較
外資におけるリスクと、どう付き合うか
GEで学んだ「ストレッチ」という発想
中途半端に優秀な人たちばかりいる会社が危ない
プライオリティづけがない分析は意味がない
日本法人の社長は単なる「支社のトップ」なのか
将来のリーダーは5分以内に判断されている
ダイバーシティは目的ではなく、ビジネスの手段である
トップが現場に行く
第6章 ジャック・ウェルチに学んだリーダーシップ-Lead by example
幹部候補生の研修で垣間見たウェルチのすごさ
パートナーの日本人100人以上の名前を覚えている
信賞必罰、強烈な厳しさで人をマネージしていく
人を育てることで、会社が良くなっていくという信念
ウェルチを本気で怒らせたことも
「プロセス」と「文化」
「リーダー」と「管理職」は違う
第7章 製薬業界とノバルティス-変化の中での新たな挑戦
変化の中に身を置けば、面白い仕事ができる
本社CEOダニエル・バセラとの出会い
まずは現場に行って、1400人以上に会う
会社の意識を変える
誰にとっても正しいこと
コンプライアンス
外資の良さと内資の良さのハイブリッド
第8章 これからの日本の役割-イノベーションが日本を変える
失われた10年
日本の医療の改革の必要性
大きな視野で日本を考える
問われているのは、イノベーションの気概
おわりに
リーダーシップが学べる推薦図書
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「世界で通用するリーダーシップ(三谷宏幸)」の購入はコチラ
「世界で通用するリーダーシップ(三谷宏幸)」の購入はコチラ 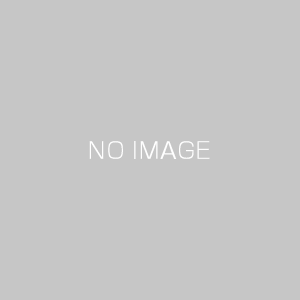
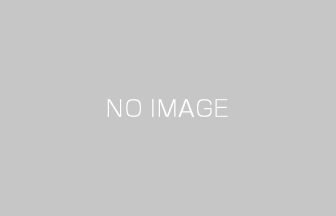
哲学がなければ、目の周りの物しか目に入らない。
哲学がなければ、目の周りの物しか目に入らない。
哲学があれば遠い未来社会が見えてくる。
盆栽・箱庭・一坪庭園など実物ばかりに気を取られていると内向き姿勢になる。
概念である ‘ユニバーサル’ (普遍的な) も’グローバル’ (全世界の) も発想の基礎とはならない。だから、日本人には世界観がない。
個人の意見は様々であるから、社会のことは政治的に決着する必要がある。
その決着のために、政治家は選出されて政治をする。
政治哲学を同じくする者同志が政党を作り、力を合わせて決着の能率を図るのが政党政治である。
だが、日本人には哲学がない。
だから、離合集散を自己利益にしたがって繰り返し、政治家たちは遠い世界を目指した政治的決着に執念を示さない。
ああ空しい。
http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/
http://3379tera.blog.ocn.ne.jp/blog/