<金曜は本の紹介>
「人生の教科書」という本は、作詞家、訳詞家、舞台の台本・演出、テレビ番組でのコメンテーターとして活躍している1938年生まれの「なかにし礼」さんが書いたものです。
本書はその「なかにし礼」さんの経験から、より良い人生を送るための教科書として、人生、若者、恋愛・結婚、死、仕事、人間関係という観点でまとめたものです。
特に以下については共感や興味を持ちましたね。
・全方位からインプットするよう少年的なあくなき意欲・意識を持つこと
・悪意は持たないこと
・成長したいという能動的な意思を持ち、努力を重ねること
・「旅」「恋愛」「読書」を正しく追求すること
・成長としようと持続することが大切
・芸術など優れた導き手を早く見つけること
・学生は純粋に友達と付き合い、笑い、遊び、本を読むことが大事
・本を読むなら19世紀の作品がオススメ。100年経っても読めるものは名作だから
・音楽も19世紀のクラシック音楽が素晴らしい
・ピラミッド・ルクソール・王家の谷は見たほうがいい
・紀元前から栄えているイスタンブールには行くべき
・無償の愛を相手に注ぐことが大切
・苦難は無駄な時間ではなく成長するための糧
・子供の苦労を排除するな
・死ぬことは「旅立ち」であると考えてほしい
・「高給」という事実は「他人の与えてくれた評価」
・仕事は全力を尽くすこと
・一度しかない人生、能ある鷹となって心を磨こう
・国際社会で生きようと思い、最低でも英語は使いこなすこと
・上司とは絶対に対立してはいけない
・ミスは認めること
・会った相手のことは褒めること
・待ち合わせ場所には相手よりも絶対に先に着いておくこと
・年輩の人と上手に付き合うには彼らの話に耳を傾けること
・人に悩みを相談し、世の中の価値観を理解すること
・本を読んで先人の教えを学ぶこと(自分の人生からはなかなか学べないことが多いため)
・いち早く本を読んだ者が勝ち
・集中して生きることが大切
・苦難を越えれば歓喜となり、苦難を与えてくれた人へ感謝の想いが発生し、そして人間的に成長する
なかにし礼さんは、本書の出版作業を進めていた2012年2月に食道にがんのあることがわかり、手術せずに治す治療で頑張っているようです。
そのような経緯もあり、本書にはかなり力が入った内容で、分かりやすく人生に役立つ言葉がたくさんあり、とてもオススメな本となっています。
とても勇気づけられます。
ぜひ読んでみることをオススメします!
以下はこの本のポイント等です。
・魅力的な人間になりたいのであれば、全方位からインプットしようとする少年的なあくなき意欲・意識を持ち続けていく、ということを永遠に続けなければならない。今の世の中は、自分の仕事や生きていく上で関係のあることだけを効率的にインプットする人間ばかりだ。ハウツーものや狭い趣味の本など、目先のことに捉われた卑近な本だけを読んでいる。私の言う「インプット」とは、そういうことではない。その方向性は360度、森羅万象であるべきで、その中でも芸術芸能に関するものが必要不可欠である。何百年、何千年という時間をかけて「優れたもの」として選ばれ続け、淘汰されずに残ってきた膨大な傑作を享受することで、世界の神髄に触れることができるからだ。また「インプットの仕方」というのも重要で、ただ漫然と対象に触れるだけではいけない。「事件」として体験することが重要なのだ。
・人として生きていく上で絶対に持ってはいけないものは「悪意」だ。嫉妬したり、人の足を引っ張ったり、陰口をたたくなど、人は無意識にそういったなんの役にもたたない感情を持ってしまうものだ。だからそれを持たないようにするには、「悪意」を自分の中から抹殺する訓練をしなければならない。そのためにはどうすればいいのか。これもまた芸術に親しむ理由の一つとなる。日常生活の中で「時間」を忘れ、「無時間」の中で芸術作品を味わう。そしてその芸術の世界に身をゆだねて、ゆっくりと身体に浸透させていく。それによって人の心の中から「悪意」が少しずつ浄化されていくのだ。なぜか?芸術作品は、悪意を持って作り上げることは不可能だからだ。
・成長とは、「成長したいと思う人だけがする」ものだ。なぜなら自分の知識や経験などに疑いを持ち、そして学んで成長するということは、すべて人の「意思」によって行われるものだからだ。だからこそ「成長したい」という能動的な意思を持ち、努力を重ねる人だけが精神的な成長を叶えるものである。まず、すべてを疑う。そしてその疑問を解明しようと考える。あらゆることを疑い、納得して先へと進む・・・そのわずかな一歩が、人の成長の扉を開くのである。
・人生のイニシエーションなしに人の成長はあり得ないのだ。ではそのイニシエーションとはどんなものなのだろうか?それは突き詰めて言えば「旅」と、「恋愛」と、「読書」だ。この3つを正しく追求して、真剣に自己の精神を鍛え上げていくことが大事なのである。
・重要なのは、成長しようとして走ることを持続することだ。走るというのは無理をすることだから、やっぱりしんどい。それでも、筋力トレーニングと同じことで、1,2,でやめてはダメで、3、4、5、6・・・というときに成長する。そして7、8、9、10・・・でやっと筋肉がつくのだ。そこまでやって初めて、自分の限界だと思っていたところが限界でなかったことを知る。そうやって人は成長していくのである。
・僕がなぜ導き手にクラシックや古典小説を選んだのかというと、それらは時代を越えて忘れ去られることなく、時の試練を耐え抜いて現代まで残ってきた、芸術家が全身全霊を込めて生み出した魂の結晶のようなものだからだ。さらにその中から自らが選んだ作品を味わうことは、偉大なる芸術家と友になることに等しく、その作品を通じて彼らと対話を重ねたことにもなる。優れた導き手によって、人は自らも高みへと上っていくことができるのだ。その真実を含んだ上で、自分を成長させる導き手を見つけ出してほしい。
・大学での4年間、この期間は純粋に友達と付き合い、笑い、遊び、そして家に帰ったら本を読み、という、当然学生がそうあるべき生活を送ることがとにかく大事だと思う。特に、本を読むこと。それが学生の本分なのだから。
・ドストエフスキーに限らず、本を読むなら19世紀の作品をおすすめする。なぜ19世紀の本を読むべきかというと、現代の本はそのどれもが真の価値が定まっていないからだ。どんなにベストセラーになっていても、それはつい最近書かれたものであり、真の価値はわからない。人々がただそのブームの中にいるだけにすぎない。しかし、19世紀の芸術には100年経ってもなお人類の宝として珍重されている作品、時の試練を乗り越えた名作がある。読書はまさに人生の勉強であり、作家という人間の勉強でもある。一人で自己鍛錬をするには読書しか方法がない。
・芸術を学ぶ際、音楽なら、黙ってクラシックを聴くこと。いまだにクラシックは不滅の音楽なのだから、それを聴くことが趣味になれば最高だ。たとえ趣味となり得なくても聴くべきである。特に、やはり19世紀の音楽。18世紀にはモーツァルトがいるけど、彼の死語、すぐベートーヴェンへ、19世紀の音楽へと繋がっていく。ベートーヴェンから始まって、シューベルト、ショパン、ブラームス、ワーグナー、マーラー、ブルックナー、ベルリオーズ・・・とにかく19世紀だ。ロマン派の時代である19世紀は、前世紀の革命時代が終わり、「人間は進化する」ことを人類が知った時代である。愛によって人間は死ぬこともできるし、愛によって罪を犯すこともできる。そして「人間は進化して神にもなれる」という、この思想を芸術家たちが作品の中に叩き込んだ。19世紀は人間の可能性のすべてを歌いきった時代なのである。
・やはり旅は「体験」するものだ。そして体験するためには残念ながら「自分が行く」しかない。これが旅のいいところだ。体験だけはデジタルじゃない。旅とはアナログなものなのだ。旅だけではなく、読書も自分で読まなければならないし、恋愛も相手と触れ合わなければならない。そして旅も自分が行かなければならない。この、「なければならない」ということがすごく大事なのだ。現代社会では日常生活のほとんどを簡便に過ごすことができる。ノートパソコンでなんでも調べることができるし、ゲームだってできる。だからその気になればまったく身体を動かすことなく、大方の時間を過ごすことができてしまう。しかし人間としての成長をするためには非日常を体験しなければならない。その中で大事なのが、読書、恋愛、旅であり、この3つが一番アナログなもの。だからこそ精神に与えるものが大きいのである。旅先で出会うものはすべて一級のエンターテインメントだ。雨が降ったり、雪が降ったり、その時々で旅先の表情は変化する。それを全身で味わうには外国に出ることだ。世界は広いということをまず知るべき。それを知らないと人間の神秘にも気付かないのだ。
・旅に出るならば1日でも早いほうがいい。自分の感受性が全部そこで晒されて、カメラにたとえるならいろんな映像を受け止めていることになる。そのインプットは大きいものだ。そしてそのインプットは日本にいてもできない類のものなのだ。
・日本の文化は確かに素晴らしいものがある。しかし、そこに踏みとどまって進化をストップしていい理由にはならない。過去の素晴らしい文化も、偉大な先人たちが勉強し、努力し、さまざまな異国の文化を吸収し、消化してアウトプットされたものだ。そう考えれば進化する努力をしていない状態は鎖国しているのに等しいと思う。
・ピラミッドを見て、ルクソールに行って、王家の谷に行く。その3箇所は絶対見たほうがいい。ナポレオンがエジプトを見て、「俺たちはいったい何をやっていたんだろう」と深刻に考えたそうだ。その気持ちは実際にエジプトに行ってみるとよくわかる。
・トルコのイスタンブールという街は紀元前からずっと途絶えることなく現在も生き続けている街だ。そんな街はイスタンブール以外にない。パリなんて街として始まったのは12世紀からだ。ニューヨーク、ロンドン、東京、みんなまだ新しい街と言っていい。紀元前から栄えていまだに続く大きな街はイスタンブールだけなのだ。ボスポラス海峡を挟んで2キロ先にアジアがあり、手前がヨーロッパという風景の素晴らしさ、東洋と西洋の文化が交差し、融合し、新たなものを生み出してきた街。人類の歴史が濃縮されたその街が今もなお残って生きている。そこに飛び込んでいくことは計り知れない刺激を与えてくれるはずだ。
・とにかく見返りを求めず、無償の愛を相手に注ぐ。そういう愛し方をするべきだ。それに相手が応えられなかったら、それは眼鏡違いというものだけど、でも、愛し続けて理解してくれない人なんていないよ。
・報われなくても、プライドを踏みにじられても、小さな存在である自分の身を嘆いても、とにかく愛し続ける、それが無償の愛だ。
・男女の正しい別れ方について強いて言うとするならば、お互いに「真実を言う」こと。これしかない。それは残酷でもなんでもないことだ。ただし、その前提として「真実を言って別れるにふさわしい付き合い方」をしている必要がある。ある程度知的で、恋愛の幻想をお互いに楽しんでいた・・・そんな二人の足跡がなければいけない。
・「人生における後悔をなるべくなくしたい」という意見があるが、理解しがたい。自分に与えられた苦難については「いい試練だった」と思えばよいのであって、その経験を後悔する必要はない。苦難を乗り越えようとする時間は人生において無駄な時間だけではなく、成長するための糧だからだ。ただし恋愛においては、後悔はしなければならない。自分が与えられた苦難はいいとしても、自分が人に与えている苦難というものもあるはずで、それについては考えなくてはならないかだ。
・僕の周りには一生独身だった人は多い。芸術家の中でも、ベートーヴェンを始め大勢いる。芸術に関わる仕事をしている人たちにとって独身であることはなんの不自由もないし、芸術活動に関して、それはむしろよい方向に作用したのではないかと思う。つまり結婚生活というのは、いかに非芸術的なものかということだ。結婚生活とは日常的な些末な出来事の連続だから、精神生活を重要視したいと思うのであれば、両立はできないと考えたほうがいい。
・もし子供を持ったら、そしてその子供を立派な人間に育てたいと思うのなら、肝に銘じておくべきことがある。それは「子供の苦労を排除するな」ということだ。多くの場合、親心というものは親の目を曇らせるものだ。自分が経験してきた苦労を子供に味わせたくない。だからその苦しみを子供が味わうことのないように手助けをしてしまいがちだ。それは言わば「親の罪」だ。親が自己満足のために子供の苦労をしている姿を見たくないという罪。そのために子供の成長過程で余計なことをしてしまう。その結果、子供は苦労知らずに育つ。味わうべき苦難を避けていると、人間的にダメな人物が出来上がってしまうことが多い。子供の成功のためには苦難は必須条件だと考えていいだろう。
・これまでの人生を詳細に振り返って、なぜ死にたいと思ったのか、その思い、その嘆きを十分に書く。己の人生の総括だ。そしてそこまで書くと人は生き返るのだ。なぜなら、自分の中にある負の意思を全部吐き出してしまうから。そしてすべてを吐き出してしまうと、書きながら、どうすればその状況から脱出できるかということが浮かんでくるのだ。つまり詳細な遺書を書くことによって、人は一度思い切り死ぬんだ。ただし頭の中で。詳細な遺書という形の「自分との対話」を残して頭の中で死んで、肉体的には踏みとどまる。ベートーヴェンはそうすることによって目覚め、「英雄」を書き、「皇帝」を書き、作曲家として劇的に成長し、その後「傑作の森」と呼ばれる数々の楽曲を生み出した。生まれ変わったことでさらなる高いレベルに進化したのだ。自分が今置かれている状況をちゃんと表現できれば、理性がよみがえってくる。だから遺書は長くなければならない。
・人間は誰もが死を免れない。そして死があるからこそ現在の生命が光り輝く。だから僕はいつも、「死を友とせよ」ということを自分に言い聞かせている。それによって生きている喜びが倍化するからだ。死を忘れて生きていると、ぼんやりとした日々を生きることになる。そういう人は生きていることがそれほど大きな喜びではない。しかし「死ぬんだ」と自覚することで、今という時間が非常に貴重になる。だからもし自分にとって大切な人が死んでしまったとしても、いつまでも悲しんでいてはいけない。死ぬことは「旅立ち」であると考えてほしい。死んだ人が旅立ったのではなく、「自分」がその人から旅立つということだ。母親でも恋人でも誰でも、その人が亡くなったということは、この世からその人が旅立っていったのだけれども、一方で自分がその人から「旅立った」と、そう感じることがすごく大事だと思う。そう思うことによって、死んだ人が自分に与えてくれたものや、よいところをいっぱい思い出すことができるし、感謝もする。旅立つということは未来に明るい展望を持っていないとできないことだ。
・「高給だがつまらない仕事(危険をともなうとか、そういう特殊な例は除く)」と「薄給だが面白い仕事」、どちらを選ぶべきか?それはもう断然「高給だがつまらない仕事」だ。つまらないかそうでないかは本人の価値観でしかないが、「高給」という事実は「他人の与えてくれた評価」だ。それは客観的な視点での結果だから、他人の与えてくれた評価のほうが正しい。簡単な話だ。
・仕事というものは、目の前に来た事柄に全力を注がなくてはいけない。好きな仕事、嫌いな仕事は関係ない。全力を尽くすことで、人間は計り知れない能力を発揮できる。これはセックスだって同じだ。みんな一生懸命やる。一生懸命やると、何か自分でも驚くような快感を得たりすることができる。セックスでできることが仕事でできないわけがない。セックスだけまじめにやるのでは困りものだ。セックスと同じくらい仕事を一生懸命やると、頭から湯気が出て、パッといいアイデアが浮かんだりする。一生懸命しないうちはダメだ。熱度というものが帯びてこないといけない。熱度を帯びると自分の力以上のものを発揮することができるのだ。そうなると人は感動してくれるし、評価へと繋がっていくのだ。
・若者よ、ドン・キホーテたれと僕は言いたい。ドン・キホーテを馬鹿にする側に回らないで、ドン・キホーテになりなさい。その瞬間、あなたは正しく生きられるんだ。自分の信念と、自分の意識と、自分の意思で生きる人になれるからだ。自分のペースで無理することないと思ったら人並みだし、人と一緒に行こうと思ってしまっても人並みだ。それでは突出することなどできない。そして一度しかない人生、能ある鷹となって心を磨こう。打たれるほどの出る杭になろう。
・語学は、最低でも英語を使いこなせるようになったほうがいい。なんだかんだ言って世界共通の言語であり、一気に自分の世界観が広がるからだ。これからは日本語にこだわっている時代ではなくなる。
・仕事をする上で上司と対立するのは能がない者がやることだ。意見が違うのはいいが、絶対に対立してはいけない。会社組織の中で二者が対立した場合、絶対に損をするのは部下のほうである。孤立するし、はじき出されるからだ。ではどうすればいいのか。まずは「上司を怒らせない」ようにすることだ。怒りは、すべての論理を飛び越えて感情に走ってしまうから際限がない。相手は自分より立場が上である。となるとこちらは逃げるわけにもいかず、ただただ怒鳴られていなければならなくなってしまう。これでは意見を通すどころではないだろう。人間関係は全部利害関係で成り立っている。だから、上司が怒りだす場合、その原因はあなたの意見によって上司の立場が危うくなったり、メンツを壊してしまうときである。自分が損をしない意見には上司も反対しないもの。だからこそ、意見を交換しつつも、上司が損をしないようにいろいろ考えをめぐらせながら、お互いに利害関係を共有しあう仲を保つようにするべきだ。そのためには上司に対して愛情を持つことが重要になる。
・仕事で大きなミスをしたときにどうすればいいか。それはもう絶対に失敗を認めることだ。言い訳はいらない。逆になぜミスを認めない人がいるのかがわからない。意味のない保身をしたいのか、変なプライドがそうさせるのか。
・人に会ったら、なんとなく褒め、逆に褒められたら褒め返す。これはゴマすりではなくて、会話の糸口なのだ。会話の小ネタといってもいい。そこから本題に入っていくときに、お互いに気持ちのいいスタートを切るための潤滑剤だと思えばいい。
・待ち合わせ場所には、相手よりも絶対に先に着いていなければならない。相手より遅く着くと会話の冒頭が「謝罪」になってしまう。遅刻した場合はもちろん平謝りだし、遅刻しなかったとしても相手が先に着いていれば、その分相手を待たせたことになるわけだから、「お待たせして申し訳ありませんでした」と謝るのは当然である。そして謝った瞬間、あなたは敗北したことになる。会ってすぐに敗北していては、待ち合わせ相手との関係性や仕事を思い通りに進めることなどできないだろう。だから絶対に遅れてはならない。どちらが誘ったかも関係ない。誘われたら誘われた者の礼儀、誘ったら誘った者の礼儀として、早く行かなければならないのだ。待ち合わせ時間ピッタリに着くなどもっての外で、待ち合わせは相手との「勝負」であると心得ておくくらいでちょうどいい。
・年寄りにとって、日々の発言は言ってみれば遺言のようなものだ。それまでの人生で学んできたことを誰かと共有し、伝えていくことで自分の存在証明にもなる。だから自然と彼らは話し好きになるだろうし、話をしたくて仕方がないほどだと思う。その人たちには敬意を持って接し、どんどん話を聞こう。必ず何かを学べるはずだ。もし、相手の話が退屈だと感じるようだったら、まずは自分の無知を疑ってみるといい。そうすれば素直に耳を傾けることができるようになるだろうし、逆に相手に質問することも多くなり、年配の人との人間関係に悩むことなんてなくなるはずだ。
・若いうちに悩みはつきものだ。でもその悩むという行為によって人はまた多くのことを知ることができるし、成長することができる。だから一人で思い悩んでいる人は、誰でもいい、誰かと相談しなさい、と言いたい。相談して何も決められなくてもいい。肝心なのは、あなたの悩みを聞いてくれる相手がいると、世の中の価値観がわかるということなのだ。「くだらないことで悩んでいるわね」と言われることもあるし、「それは大変だ・・・」と聞いてくれる場合もある。人に相談することで自分ではわからなかった、自分の悩みが「いかにくだらないもの」だったか、または「重大なもの」だったかということがわかるのだ。一人で悩み続ける人はどこかで社会性というものから自分を遠ざけてしまっているから、「人間関係」という生きていく上で一番大事な部分が弱くなってしまうし、「人を好きになる」ことも難しい。「人を愛する」という、価値あることをしないでいて、自分のことで悩むのは言ってみれば怠慢だ。「怠慢」と「臆病」、「無知」というのは、人間の三大欠点。この病に陥らないようにしないといけない。
・成長して恋愛して、振られて人を傷つけて、なんだかんだいっても人生これの繰り返しだ。それが作品として残っている本がある。我々はそこから学ばずして、いったい何から学ぶというのだ。自分の人生から学ぶことなど極めて少ない。だから他人の生きた経験、そこで考えたことに共鳴することによって、いろんな人の人生を「生きること」ができるし、充実した人生を送った先人の残した記録から学ぶことはとてつもなく大きいのである。その本は何もドストエフスキーだけじゃない。何かに目覚めて突然宇宙の本を読んでそこに耽溺したり、突然マルクスに目覚めてもいい。なんでもいい。しかし1冊や2冊の本ではダメだ。長時間自分の魂と脳みそが燃え続けるということが大事だ。燃え続けるマラソンでなければいけない。そして必ず完走すること。肝心なのは何時間で終わったといった記録ではなく「集中したまま完走した」という結果だ。だから本を読むのが1ヶ月かかってもいい。あまり途中下車しないで、集中して読み終えて本を閉じる。そのときの喜びを味わったことのない人とは僕は友達になれないとさえ思う。
・人は誰もが生まれたときには平等だ。ガキで無能で、どうしようもない男の子や女の子だ。でも物心付いて思春期が終わったあたりから一斉にすべてがスタートする。そのときにいち早く本を読んだ者の勝ちだ。その際に覚えておかなければならないことは、「集中して生きる」ということだ。意思があろうと、意識が高まっていようと、集中する能力がなかったら何もできないからだ。
・個人的な能力差もあって、能力が低くて早くできない、仕事ができないという人もいるだろう。そういう人は集中力が全然足りない人だ。集中力とはその人の「意思」だ。だから自分の意思を強く持って集中しなけえばいけない。それができない人は、きっと何をやってもできないと思う。誰でも何かに夢中になって脇目も振らずに集中した経験があるはずだ。それを思い出して今度は自然に任せるのではなく、自分の意思で集中してみればいい。集中して困難な波をついに越える。そこで待っているのは「快感」だ。
・快感イコール、歓喜でもいい。要するに「喜び」だ。喜びを得ないと次がない。だから苦難を乗り越えて喜びを見出し、また苦難を乗り越えて・・・これの連続だ。そしてここが重要なのだが、苦難を与えてくれる仕事でもなんでも、「越えれば歓喜になる」ということは、その苦難を与えてくれる人、仕事を与えてくれる人への感謝の想いになる。それが次の仕事に繋がり、物事が回り始めるのだ。やり遂げたことで歓喜を得る。それによって人は誰かに感謝できるようになる。信仰のある人は神でもいいし、上司に対する感謝でもいい、そういう人生に対して感謝してもいい。でもその感謝の想いがないと、いつまで経っても人間的に成長することはないだろう。自分の人生とはいろんな人のいろんな想いによって支えられているということを理解するだけで人は成長できるのだ。
<目次>
人生
自分の存在を全肯定せよ
「大人」になるな!
「悪意」を徹底的に排除せよ
「疑うこと」なしに成長はなし
成長に必要な3つのイニシエーション
成長すると時間の感覚が変わる
人生の「導き手」を一刻も早く見つけよ
若者へ
草食系男子万歳!
若者言葉は高等技術である
絵文字はどんどん使え
暇な大学生活のすすめ
「カラマーゾフの兄弟」を読め!
なぜクラシックを聴くべきなのか
環境音楽として流す-などあり得ない
本物の「遊び」の流儀
恍惚こそ酒の醍醐味
日本人ならば日本の達人になれ
夢がなければ旅に出よ
日本には限界がある
ピラミッドという衝撃を体験しろ
トルコで自分の中の神秘を知ろう
恋愛・結婚
愛するとは、見返りなしでも優しくすること
恋いとは自分の意思で落ちるもの
自分を卑下する気持ちが無償の愛
恋愛は幻想であるべきだ
恋愛はルール無視の暴走である
恋の上手な終わらせ方
恋愛とは後悔の連続である
結婚とは「死」に似たもの
結婚生活は「1+1=2」ではない
夫婦のシステムはもっと変わるべき
子供を作るなら苦労させろ
死
自殺したくなったら遺書を書け
死こそ人生で最もこだわるべき儀式
葬式の演出は生きているうちに考えろ
死を友とせよ
仕事
「高給」は自分への評価だ
仕事はセックスだと思え
ことわざに振り回されるな
言葉を学ばなければ仕事にならない
外国語は国際人へのパスポートだ
外国人と上手に仕事をする方法
上司とは対立するな
「プライド」ほど人生で無駄なものはない
会話は「プチ礼賛」でうまくいく
待ち合わせは「戦い」であると心得よ
招待される心得
たとえ偉くなっても威張ってはいけない
電話の作法① 電話で普段通りに話すな
電話の作法② かかってきた電話には早く出るな
手紙の作法① 手紙とは形式の美学だ
手紙の作法② 手紙は青インクの万年筆で書け
人間関係
なぜ人には裏の顔があるのか
人脈作りの極意は「相手に幸福を与える」こと
親友について① 真の友は大切な人脈から生まれる
親友について② 同じ夢を語れるかどうか
親友について③ 異性の親友はあり得るか
男らしさは優しさ、女らしさも優しさ
苦手な相手への対処法
フェイスブックのすすめ
年寄りの話は無条件に喜んで聞け
人に悩みを相談して価値観を学べ
エピローグ
人生の荒波を越えるために読書で力を養え
苦難を克服すると快感が待っている
あとがきに代えて
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「人生の教科書(なかにし礼)」の購入はコチラ
「人生の教科書(なかにし礼)」の購入はコチラ 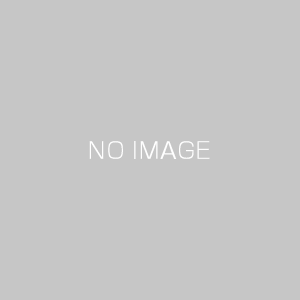
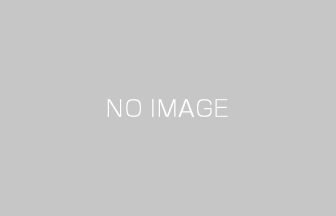
いつもブログを拝見しております。
いつもブログを拝見しております。
この本は、なかにしさんが大病されて
から出された本で、以前以上に
思い入れが伝わってきます。
先日ご紹介してくださいました
「ニーチェの言葉」を早速読んでおります。
いやー、人生観がかわりました。
ニーチェというと、一般的に、難しくて
それが、簡単に解説されており
図書館から借りて読んでいるのですが
これ購入したいと思います。
さて、いま自分のお勧めは二冊。
・宮崎奈穂子著
「路上から武道館へ」中経出版
・左巻建男
「水はなんにもしらないよ」
よろしければ、どうぞ。
ヒッキーさん
ヒッキーさん
コメントありがとうございます!
その2冊はぜひ読みたいと思います。