<金曜は本の紹介>
この「酒場を愉しむ作法」という本は、いろんなスタイルの酒場やいろんな方の酒飲みの作法、酒の種類などを紹介していて、酒飲みには堪らない本です^_^;)
特に、具体的にそのお店の連絡先等を紹介していのもうれしいです。
私もいくつかこれらのお店を訪れてみたいと思いました。
とてもおすすめな本です。
以下はこの本のポイント等です。
・梅田の夜は早い、というか早過ぎる。昼過ぎには飲みだし、夕方3時ともなるとぼちぼち混みだし、夕方5時には店がいっぱいになる。混みだしてくると、客は自然と右斜め45度の立ち姿となり、これをいつの頃からか知らないが、ボーカルグループ「ダークダックス」にちなんで「ダークする」と言うようになった。満員でも右手さえカウンターに届けば、串をかじり、飲む、と事足りる。最近は東京でも立ち飲みがブームになっているが、大阪では何十年も前から立ち飲み屋が繁盛し、飲兵衛たちはダークしていた。
・和歌山県の高野山は、およそ1200年前に弘法大師・空海(774~835)が開いた高野山真言宗の総本山である。標高900メートルの山頂部分に、人口4000人の宗教都市が突如現れる。暮らす人は修行僧とその家族がほとんど。だから建前上、居酒屋もなければ、酒もない、ことになっている。宿泊先は、「宿坊」と呼ばれる寺院。遍照光院という格式の高い宿坊にお世話になる。夕食はすべて植物由来の精進料理である。ごま豆腐などの名物料理もさることながら、やはり旅先だけに飲んでから休みたい。そんな下賎な心根を見透かしたかのように僧侶は、「泡般若をお持ちしましょうか」と、ビールを出してくれた。聞き慣れない呼び名だ。僧侶の話では、弘法大師が零下数十度となる真冬の高野山で凍える弟子を見かねて、体を温める目的に限って「いっぱいの般若湯は許す」と仰せになったそうだ。般若湯とは日本酒のこと。ビールは泡が立つから「泡般若」なのだそうで。「麦般若」と呼ぶ向きもあるそうだ。聖者の慈悲深いエピソードが愉しくて調子に乗って、もう一本ビールを頼んだ。僧侶はにやりと笑って「お大師様(弘法大師の呼称)は、いっぱい、と仰ったのですが、コップに一杯なのか、腹いっぱいなのか、これは今も解釈が分かれるところです」。無論、腹いっぱい説を推すこととして、3本目のビールを飲み干した。
・ワンコインの立ち飲み店、といっても500円玉ではない。料理がほぼ全品100円という激安店がある。JR秋葉原駅近くの雑居ビルの2階にある立ち飲み店「スタンディングバー百飲」がそれだ。夕方5時からの営業時間を待って、連日大勢の客が詰めかける。6時を過ぎると店内はすし詰め状態。狭い廊下には入店待ちの行列ができる。店に入ると、カウンターに何層にも重ねられた小鉢が目に入ってくる。客は選んだ小鉢をレジに持って行き、会計と同時に酒を注文。そして、島状に散らばった小さなテーブルで飲み食いする。料理はどれも基本的に手作りで、味つけはあっさりしている。豪華さこそないが、素朴で旨い。煮込み、焼き魚、肉じゃが、冷や奴、おひたしやコロッケ類など、家庭料理風のつまみのほとんどが100円。揚げたて天ぷらなど200円のメニューもあるが、この値段でちょっとした贅沢気分に浸れるのはうれしい。店主いわく、「安さの秘密は、手作りが多いこと」だとか。「冷凍食品ばかりを使っているとコストが高くなる」ということで、店主は手間を惜しまずカウンター内でさまざまな料理を矢継ぎ早に作り続ける。生ビールは中ジョッキ200円。ウイスキーは「角」がシングル100円、ダブル200円。普通に飲み食いしても1000円でおつりが来る。
・JR浜松町駅北口から徒歩3分ほどのところに「名酒センター」がある。この名称から大型酒飯店のようなものを想像するかもしれないが、実際は商店街にある子規模な酒屋ほどの間口で、外観はこぢんまりとしている。ところがなかに入ると、「センター」と名乗るだけの所以がわかる。3つある冷蔵ケースにびっしりと陳列された全国各地の蔵元自慢の日本酒は、ざっと100種類。来館者(このセンターでは客をこう呼ぶ)は、好きな銘柄を3つ選び、3杯500円(1杯だと200円~)で飲み比べできる。酒は、お猪口がちょうど3つ横に並ぶ、小さく可愛らしいお盆で提供される。数々の日本酒を囲むように据えられたテーブルでちびちび飲むと、やはりつまみがほしくなる。バラ売りのせんべいやクラッカーなど乾きもの、おひたし、塩辛、梅しそなど小鉢の用意もある。量といい、組み合わせといい、日本酒好きのツボを心得たさじ加減が心に染み入る。このように軽くつまみながら利き酒を愉しめるだけでなく、日本各地の酒蔵直送の日本酒販売や地方発送、それに蔵元を訪ねるツアーや試飲会など不定期での各種イベントも開催している。
・「東京の繁華街のなかで、”飲酒文化”があるのは銀座だけ」と主張する人がいる。その是非はともかく、銀座には伝統と格式をもった酒場が多いのは事実。「ルパン」「ボルドー」のような老舗バーもいいが、銀座にも「三州屋」「樽平」など親しみやすい居酒屋も少なからずある。銀座に隣接する新橋は、ずっと庶民的なサラリーマンの街。古い時代には花街として賑わったが、いまは大衆酒場が密集する街である。会社帰りにちょっと一杯だけやっていきたい勤め人の需要からか、立ち飲みも多い。「竜馬」はそんなチョイ飲みに最適の一軒だ。その他、都心部では、老舗の風格ある居酒屋はあちこちに分散しているように思われる。有名なところでは、「みますや(神田)」「鍵屋(根岸)」「シンスケ(湯島)」「伊勢藤(神楽坂)」「岸田屋(月島)」など。初めて訪れる客は、風格に気おされて畏まってしまうような店もある。しかし、基本的なマナーさえわきまえていれば、どんな店でもくつろいで酒肴を愉しめばいい。都心部の酒場は、おおむね良い意味で個人主義的。店と客も客同士も関係がべたつかない。交わりは淡きこと水の如く、純粋に酒と肴に向き合うのが都会の流儀だろう。
・旨くて安い魚が食べたいときは、築地へ行くといい。市場の北側にある築地本願寺の裏手には、鮮魚の卸売業者、中卸業者ら魚のプロを相手にするこぢんまりした居酒屋が何軒もある。無論、素人もその恩恵にあずかることができる。だがそのほとんどはインターネットで検索しても、電話番号すら判明しない。ある店の主人は「店が狭いから宣伝してもね。職場から歩いて来てくれる範囲のお客さんを相手にするだけで手いっぱいだよ」と笑っていたが、素人に大挙して押しかけられても30席ほどの店では対応できない事情もあるのだろう。2センチ角程度のマグロのぶつ切りが10個以上入って300円、アジの開きが200円だったりする。驚くべきはその新鮮さである。3~4人で刺身の盛り合わせを3000円分も頼めば、旬の魚介類を目いっぱい堪能できる。「この値段で、こんなに旨いのか」といううれしさで、酒も進むというものだ。
・おかしなもので、目の前のつまみがなくなると、店側も客側もなんとなく注文しないとバツが悪いような雰囲気になり、そわそわしてくる。そのためにも手をつけないつまみを残しておくのが、少ない金額で酔える技だ。そのつまみを残したにらみ豆腐という言葉は、酔っ払いながら生き、酔っ払いながら小説を書き、酔っ払いながら階段から落ちて死んだ、中島らも(1952~2004)の言葉だ。彼のエッセイか何かで読んだのだが、実は読む前からこれを実践していた。酒飲みならば、自然と身につく極意の一つなのだろうか。
・J氏はまるっきりの下戸。乾杯のビールに口をつけただけで顔が真っ赤になり、しばらくするとぐったりして目もうつろになる。そして、その翌日は丸一日寝込んでしまうほどなのだという。そんなJ氏が、なぜワインの販売を正業としているのだろうか。J氏は若い頃、自宅近くのフランス料理店で、下戸なのに白ワインを注文した。フランス産で3000円程度のワインだったそうだが、口にしてもなんの違和感もなく飲め、それが体にしみ通るほどおいしかったのだという。フルボトルを半分ほど空けたにもかかわらず、酔い潰れることもなく歩いて帰宅し、翌日も宿酔も悩まされることもなかった。ちなみにJ氏は残ったボトルを自宅に持ち帰り、冷蔵庫で保管して翌日飲んでみた。すると、「昨日とまったく味が違う、まずい・・・・」と途端に頭痛に襲われた。後日、件のフランス料理店のオーナーにその話をすると、彼はJ氏に生産地から日本まで温度や湿度を保って運ぶことの難しさなど、ワインの鮮度管理についていろいろと教えてくれた。J氏は下戸だからこそ、微妙な鮮度の変化を敏感に感じ取ったのだろう。その後、J氏は「下戸の自分でも飲める鮮度の良いワイン」探しにはまり、ワイン専門学校、輸入会社勤務などを経て独立したというわけだ。「自分でも飲めるワインを売れば、味に間違いがない」と舌ならぬ体で選んだワインの品質レベルは高い。産地からの鮮度管理が失敗したものは、香りを嗅ぐだけで「これは飲めない」とわかるという。高級志向はない。「安くてもおいしいワインを皆に愉しんでもらいたい」ことがすべてという。自分が飲みに行きたい店があったら、状態のいいワインを惜しみなく提供するという。
・横須賀は、旧帝國海軍の軍都だった。今も街の繁華街には当時の面影が残る。当時、海軍の高級将校たちが贔屓にしていた料亭が何軒かあり、その一つ「小松」は今でも米ヶ浜で営業している。横須賀に鎮守府ができた明治初期からのこの老舗は「パイン(pine=松)」の愛称で歴代の提督たちに親しまれた。店には彼らの酒席での様子が語り伝えられている。馴染み客だった東郷平八郎は、日露戦争の戦功で神格化され、というより東郷神社の祭神として本物の神様になってしまったが、飲めば南国薩摩風のひょうきんな一面もあったらしい。山本五十六は酒脱な粋人だった。店内に展示された提督たちの揮毫を見て、旧海軍を偲びながら飲んでみたい。
・変わり種のビールといえば、真っ先に思い浮かぶのがベルギービール。言うまでもなく、ベルギーで生産されるビールの数々である。イチゴやモモなどのフルーツ味、大麦ではなく小麦を原料にしたものなど、変化球のオンパレードである。砂糖が入っているものが多いので、あっさり系の国産が好きな人にはどぎつく感じるかもしれないが、暑い夏にはすっきり飲めるはず。厳格に麦芽やホップなどの製法にこだわる正統派とはいえないが、おおらかに飲んで愉しみたい。
<目次>
まえがき
第1章 酒に交われば
店構えで店の心を読む
ひとり酒はコの字に酔う
立ち飲みは「ダークして」「膨れる」
一見を愉しむと酒場は聖地となる
「角打」で缶詰に舌鼓を打つ
マイ箸にマイお猪口
気になるライバル店の暖簾を潜る
第2章 店に交われば
酒場の理想郷は店が店主を手伝う
幻の”路上飲み場”
自分を見つめ直すいい機会とする
日本酒百貨店で日本酒愛に浸る
牡蠣と酒のベストマッチをオイスターバーで探求する
スプーン片手にカレーとビールを流し込む
第3章 街に交われば
奥深い東京の”地霊が宿る”酒場たち<徘徊酔人のすすめ>
都心<酒と肴に向き合う都会の流儀を味わう>
東京東部<軽い憎まれ口の応酬が挨拶がわり>
東京北部<街道沿いに庶民的な酒場をめぐる>
東京南部<新鮮なモツに酎ハイをあわせる>
東京西部<ゴールデン街発中央線の酒旅>
中目黒<酒場激戦区で人情に触れる>
かっぱ橋道具街<酒場の道具がそろう街に居酒屋は・・・・>
築地市場<プロの職場の流儀に従い酒肴をもてなす>
第4章 人に交われば
希代の名文家・内田百聞の作法<70歳にして毎日欠かさず五合酒>
酔っ払い続けた奇才・中島らもの作法<にらみ豆腐とチャカチャカ酔い>
一代の遊蕩児、永井荷風の作法<紙を知れば酒益々味あり>
蕉門十哲の俳人・宝井其角の作法<居酒屋で句を詠む>
旅と酒を愛した歌人・若山牧水の作法<酒で魂を「あくがれ」させる>
フランスの名画「ベティ・ブルー 愛と激情の日々」の作法<陽気に飲み笑う様が哀しみをより濃くする>
歌舞伎の大酒飲みの作法<酒を浴びても忠義を忘れず、酔った勢いでも無念を晴らす>
下戸のマスターの作法<自分が飲める鮮度の高いワインを探す>
バー・オーナー弁護士の作法<自分のためにバリアフリーの酒場>
第5章 ニッポンに交われば
酒仙に思いを馳せて<斎藤酒場の流儀>
浮世絵の酒宴に思いを馳せて<女に武者に料理屋での句会>
「教訓親の目鑑 俗二云ばくれん」 喜多川歌麿(1753~1806)
「誠忠義臣名々鏡」 一勇斎(歌川)国芳(1797~1858)
「江戸高名会亭尽」歌川広重(1797~1858)
気負うことなく酒の感興を謳う<和歌、俳句のなかの酒>
1200年以上前の酒<万葉集にみる酒を飲んでの喜怒哀楽>
大伴旅人
大伴坂上娘女<大伴旅人の妹で万葉集を代表する女流歌人>
一杯一杯復一杯、酒の美意識に連綿と流れる<漢詩のなかの酒>
第6章 酒と蘊蓄
日本酒九種を把握する
「カップ酒」から日本酒の旅に立つ
吟醸酒を知り日本酒通になる
暦と酒、風流を感じる
花見酒
みそぎ酒
月見酒
雪見酒
年に一度、梅酒の饗宴を愉しむ
変化球のオンパレード「ベルギービール」を愉しむ
2月14日の特選地ビールを愉しむ
ワインであってワインでないボジョレ・ヌーボーを愉しむ
待つのを愉しむおでん屋の酒たんぽ
酒と焼き鳥と柚子胡椒
沖縄原産は泡盛にあらず、ラム酒にあり
コラム①酒場のない山頂で「泡般若」「般若湯」を
コラム②パワースポットで滝の水が酒になる?
コラム③湯船に浸かって一杯、じんわり体に染み渡る
コラム④話さない者同士に相通じる何かを思いやる
コラム⑤旧帝国海軍を偲びながら飲む<神奈川・横須賀その1>
コラム⑥ぺりー来航の港町・浦賀の老舗に酔う<神奈川・横須賀その2>
あとがきに代えて
<今日の独り言>
Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。
 「酒場を愉しむ作法」の購入はコチラ
「酒場を愉しむ作法」の購入はコチラ 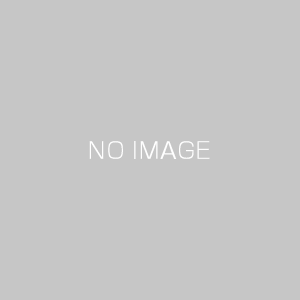
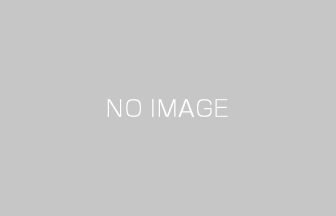
とても魅力的な記事でした!!
とても魅力的な記事でした!!
また遊びにきます。
ありがとうございます!!
ビジネスマナーさん
ビジネスマナーさん
コメントありがとうございます!
また来てください!